[本ページはプロモーションが含まれています]
私は認可外、認定子ども園、企業主導型など様々な保育園を15年間に渡り歩いている男性保育士です。
これまで「給料の低さから、このまま保育士を続けても良いだろうか?」「自分の子どもとの時間が取れない」等と感じ転職を繰り返してきました。
しかし、結局は保育士に戻っていました。それは保育士という仕事が私にとって魅力的だからです。
Webで検索すれば沢山の情報が出てきますが、その多くは一般的な内容で、あなたが本当に知りたい「男性保育士のリアルな声」は少ないかもしれません。
だからこそ本記事では、私の経験をもとに、男性保育士の仕事の魅力ややりがい、給料、労働環境、人間関係といった「しんどさ」や「難しさ」まで、現場のリアルな情報を包み隠さずお伝えします。
保育士の仕事と役割
まず大前提として、保育士は単なる「子守り」ではなく、子どもの「育ち」を支える専門職です。
私たちは国の定める「保育所保育指針」に基づき、一人ひとりの子どもの心身の発達を援助するという、専門性の高い役割を担っています。
その仕事内容は多岐にわたります。
- 子どもの生活援助(食事介助、トイレトレーニング、着替えの補助等)
- 保育活動(子どもの発達段階に合わせて、成長が期待できる遊びの導入)
- 保護者対応(日々の様子のお伝え、連絡帳の記入、育児相談等)
- 事務作業(指導計画、日誌、行事計画、個人記録、リスク管理等)
- 行事の指導(運動会、生活発表会、卒園式等)
これは男女関係なく、保育士が連携して行う業務です。自分のクラスのことだけを把握するのではなく、園全体の行事計画や別のクラスの子どもの様子まで、しっかりと確認して進める必要があります。
そのためには、保育士同士の連携は欠かせません。必ず伝達事項を伝えたり、日々の保育活動やクラスの子どものことを相談したりするなど、保育園では日常的に行われています。
数字と実態で見る!保育士の労働環境
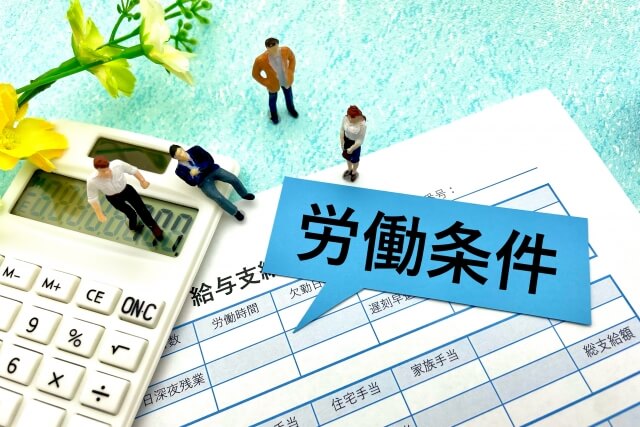
やりがいがある一方、その労働環境は決して楽なものではありません。ここでは具体的なデータと私の経験を交えて解説します。
保育士の勤務時間と一日の流れ
「保育士は朝早い」「帰りは夜遅い」というイメージは、残念ながら事実です。
保育士の勤務時間は、基本的にシフト制で多くの園が早番・中番・遅番の3交代制を導入しています。
これは、どの時間帯でも子どもたちに対して保育士の人数が確保できるからです。
一日の流れ(中番の場合)は以下の通りです。
- 8:30 出勤・伝達事項の確認
- 9:30 朝の会、主活動(散歩、製作など)
- 11:30 給食
- 13:00 午睡(この間に連絡帳記入、会議、活動準備、休憩)
- 15:00 おやつ
- 16:30 順次降園、保護者対応
- 17:30 掃除、明日の準備、退勤
現状、保育園の職員人数にもよると思いますが、定時で帰宅できることも増えてきました。
しかし、発表会前には衣装や大道具を作るために連日の残業がありますし、膨大な量の書類作成が終わらず、家に持ち帰って仕事をすることも日常茶飯事です。
また、休憩はお昼寝の時間に設定されていますが、日々の製作準備や気になる子どもの話し合いなどで、休憩できないこと多々あります。
このような労働時間における悩みは、男女関係なく、全ての保育士が向き合わなければならない現実です。
ちなみに、一般的な保育園の場合、24時間保育施設でない限り夜勤はありません。夜勤があるのは、夜の営業が盛んな地域が多い印象です。
保育士の休みと年間休日
保育士の休みは、日曜・祝日が基本です。一般的に保護者の労働を支援するため、保育園は土曜日や盆休みなども開園しています。
保育士はシフト制のため毎月、1〜2回の土曜日出勤があります。そのため、年間休日は110日〜120日が一般的で、カレンダー通りの休みを期待するとギャップを感じるかもしれません。
有給休暇の取得も権利としてありますが、「先生たちに迷惑がかからないかな…」とためらってしまうこともあります。
保育業界は深刻な人手不足に陥っており、一人が休むと残りの職員に大きな負担がかかるためです。
そのため、「熱を出した子どもを看病する」といったやむを得ない理由以外で有給消化するのは、心理的に難しいと感じる保育士が多いのが実情です。
また、園長や主任が厳しい態度で管理している保育園だと真面目な態度を求められるため、「休むと小言を言われそう」「有給消化しづらい」と感じる保育士もいます。
好きなときに休みが取りにくいのは、保育現場のリアルな課題と言えるでしょう。
男性保育士の身だしなみ
男性保育士として働く上で、身だしなみは気にする必要があります。私自身、「清潔感」「動きやすさ」「安全性」の3つに気をつけています。
- 服装
- 髪型・ひげ・爪
- 脱毛(ムダ毛ケアのこと)
Tシャツやポロシャツに、ジャージやチノパンが基本。フードや紐付きの服は、子どもが引っ張って事故につながる可能性があるためNGです。
髪は短く清潔にしましょう。ひげは基本的に毎日剃ります。爪は子どもを傷つけないよう、常に短く切っておくのが鉄則です。
必須ではありませんが、夏場に半ズボンを履く際など、清潔感を意識してすね毛のケアを行う男性保育士もいました。子どもが面白がってすね毛で遊ぶこともあるので、保護者からすると不快に感じる場面かもしれません。
私自身はエプロンを使用していないのですが、保育士のほとんどは可愛いキャラクターが描かれたエプロンをつけて仕事をしています。
基本的には衛生面上からエプロンは外した仕事着(園によっては制服がある)で出勤しますが、そのままエプロンをつけて園へ出勤し、勤務後に買い物に行く保育士もいる姿は良く見かけます。
また、子どもから嘔吐されたり、ふいにお茶をこぼされたりと、アクシデントで洋服が汚れることも考え、着替えを用意しておく工夫は必要です。
保育園での保育士の男女比
保育士全体における「男性のパーセンテージ」は5%と少数派です。ですが、2000年の頃は約1%だったため、その割合は着実に増えています。
上記は保育士資格を取得し登録をしている割合のため、実際はもっと多くいますが、現状少ないのは変わりありません。
原因としては、やはり給料が低く、新卒の年収は、約340万円とかなり低い傾向にあります。そのため離職率が高くなり、男性保育士が増えないのです。
また、30代後半に差し掛かると、今度は仕事の持ち帰りや残業で、自分の子どもと関わる時間がない現実も離職理由の1つです。
出典:こども家庭庁「保育士登録者数等(男女別)」
出典:令和6年賃金構造基本統計調査
保育園での男性保育士の必要性と「あるある」な仕事内容

先程、簡単に離職理由についてもお伝えしましたが、保育士をしていると感じる男性保育士の必要性や仕事での「あるある」を紹介します。
(1)男性保育士の必要性、特徴
男性保育士は主に下記の3つの理由から必要と考えられるようになりました。
- 子どもの「好奇心」と「運動能力」を引き出すことができる
- 防犯上の重要な役割
- 女性保育士とは異なる視点
男性保育士はダイナミックな遊びができることから、子どもたちにとって「やってみたい」という好奇心を物理的に解決できます。肩車や鬼ごっこなどから、運動能力やルールを教えられる重要な役割があります。
また、防犯面では、園内にいるだけで安心感を与えられる存在です。それだけでなく、男性特有の論理的な視点は子どもの発達を客観的に分析するために大切な役目を果たします。
(2)男性保育士のメリット
男性保育士のメリットには、女性保育士、保護者から頼りにされる機会が多いことが挙げられます。男性保育士は力仕事や高所の作業を任されることが多いです。実際、私も多くの園内整備をしてきました。
特に男性保護者からは、「妻はこう言っているんですけど、納得できなくて…実際はどうですか?」と子育てのアドバイスを聞かれることも多いです。
自分でも頼られると感じると自己肯定感が上がり、「この仕事をやっていて良かった」と感じることもメリットと言えます。
(3)男性保育士が気をつけること
まずはハラスメントです。実際に男性保育士が女児の着替えを盗撮したという事件も起きたことがあり、慎重にならざるを得ません。
実際、女児のお尻に触れないような抱っこをしたり、子どもへの過度なスキンシップは避けたりしています。
また、若手の女性保育士に「可愛い」と言ってしまうことで、「気があると勘違いされて気持ち悪いと思われないかな」とハラスメントになる可能性がある接触や言葉には気をつけるようになりました。
(4)男性保育士の職場での人間関係、不安、やりにくいこと、違和感はある?
女性社会の職場のため、職員との距離感は非常に大切です。距離感を間違えると悪意を感じる噂話が起こることもあるからです。
「先生は仕事が出来ないのに指示だけ出す」「あの人とは一緒にクラス担任したくない」などの愚痴は保育園では良くあります。
誰にでも同じ態度かつ、その人をリスペクトすることが女性の職場で上手く回るためのコツだと私は感じています。
近すぎず、ドライになりすぎず、全員と適切な距離感が大切です。始めは難しく感じるかもしれませんが、慣れると自然にできるので安心してください。
また、男性保育士が保護者から嫌がられるという世間の風潮には違和感があります。
女児のトイレ介助などを男性保育士が行うことは、一般的に保護者が嫌がられると言われています。
しかし、実はそんなことはありません。男性保育士の私でも女の子のトイレの様子を確認し、オムツや下着の着替えを手伝うことは日常茶飯事です。
実際、誠実に園児の様子を細やかに伝えれば、保護者に信頼され、逆に「先生に担任して欲しかった」と言われることも多いです。
(5)男性保育士の求人状況
男性の求人状況ですが、一昔前に比べると増えてきました。求人には「男性保育士歓迎」の文言があったり、男性保育士特化の転職エージェントも存在したりしています。
以前の話になりますが、「男性保育士」というだけで面接を断られたこともあったので、良い時代になりつつあると感じています。
(6)男性保育士の給料、年収
男性保育士の平均年収は約400万円と言われています。実際、私が以前勤めていた園と現在勤めている園の年収を表にしてみました。
| 以前の園 | 今の園 | |
|---|---|---|
| 年収 | 約430万円 | 約250万円 |
| 月収 | 約30万円 | 約20万円 |
| 雇用形態 | 正規 | 契約 |
| 役職 | 専門リーダー | × |
| 勤続年数 | 9年 | 3ヶ月 |
| 処遇改善、各種手当、賞与 | 〇 | × |
上記の表から分かるように、雇用形態や役職によってかなりの違いが生まれます。保育園の給与は税金から賄われており、処遇改善手当で月額6〜8万円ほどの差があるのです。
さらに園によって住宅手当や交通費、固定残業代など加算されます。
保育士は残業が多いと言われる仕事の1つですが、残業代はきちんと支払われるケースが多いです。ですが、それは申請しなければ残業代は出ないので注意してください。
自分の自己満足を満たすために製作準備に時間がかかるのは、残業代が出ないこともあるのです。
基本は、運動会や発表会の準備や、職員不足で残らないといけない等の正当な理由がなければ残業として扱われないと考えましょう。
(7)男性保育士のやりがい
私が感じる男性保育士のやりがいは以下の2つです。
- 保育士から頼られるリーダー的存在
- 男性保護者との強い信頼関係
男性保育士は、保育園に1人か2人ほどしかいないのが現状です。そのため、頼られる存在として子どもたちの前に立つ機会が増えます。
その影響力から自然と周りの女性保育士や園長から信頼を得やすく、保育士からの頼まれ事や相談を受けることが多くなるのです。
会議での発言をしっかりと聞いて貰えたり、園全体の管理を任せられたりと活躍する場が増えていきます。
また、園児の父親とも信頼関係が築きやすいです。男性の保護者はパートナーとの育児の方向性で悩むこともあり、その時に相談できる強い味方が男性保育士です。
父親は「自分の子どもは競争心がないからどうすればいい?」「うちの子は戦いごっこが好きで相手するのに疲れる」など男性特有の悩みを持っています。
女性保育士よりも話しやすい男性保育士がいれば、「先生ちょっと聞きたいんだけど」と頼りにされ、アドバイスをもとに「助かった」と喜んでくれる姿を見ることは大きなやりがいです。
(8)男性保育士の退職(離職)理由で多いものは?
一般的に保育士の退職理由で多いと言われているのは、以下の3つです。
| 1位:人間関係 2位:給料の低さ 3位:仕事量の多さ 参考:厚生労働省「保育士の現状と主な取組」 |
私自身も人間関係でもつれたことはありますし、給料は低いです。仕事量の多さはおそらく「働き方改革」の影響からか書類の簡素化が進み、さらにICTの出現から少なくなりました。
私を含め、周りの男性保育士を退職した理由を紹介すると次の通りです。
|
これは上記の退職理由とリンクするところがあります。男性は社会的な責任を強いられることがあるため、頼りにされる反面、矢面にさらされたり、責任感から疲弊したりするケースがあることは覚えておきましょう。
男性保育士の魅力と将来性

男性保育士は非常に貴重な存在です。他の福祉系の職業でも、ここまで男性が少ない業種は余りないでしょう。
その希少性から、園内で独自の価値を発揮し、他の職種とは違った経験を積める可能性があります。
女性の職場だからこそ、男性ならではの客観的な視点や異なる発想が、業務改善や円滑な人間関係の架け橋となることも少なくありません。
そうした中でリーダーシップを発揮し周囲の信頼を得ることで、園の保育の質をさらに高める存在になれるでしょう。
また、その貴重な保育経験は、園の外で新たなビジネスチャンスに繋げることも可能です。
具体的には、おもちゃのサブスクや保育ICT事業など、現場の声を求める企業に専門知識を提供するアドバイザーとなったり、あるいは独立してベビーシッターとして、自分の理想とする保育を形にしたりと、キャリアの選択肢は多岐にわたります。
あなたはどっち?男性保育士に向いてる人・向いてない人
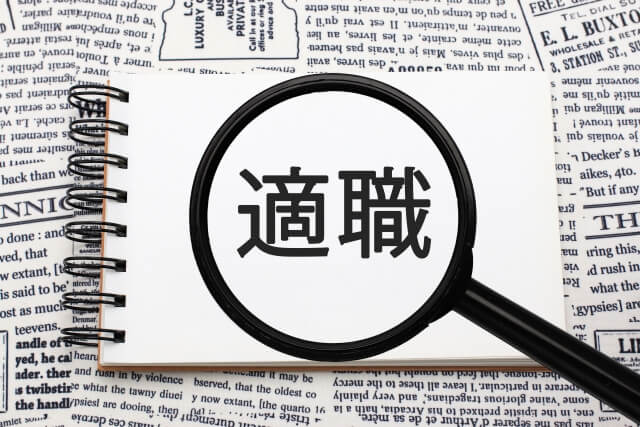
最後に、男性保育士にはどんな人が多いのか?そして、どんな人が向いてるのか?私の独断と偏見も交えてお話しします。
私の周りにいた男性保育士は、明るく元気で体力があり、子ども目線で物事を考えられる心優しい人が多いです。
【男性保育士に向いてる人】はこんな人!
- 何よりも子どもが心から好きな人
- 体力に自信があり、体を動かすのが好きな人
- 感情のコントロールができ、忍耐強い人
- チームで働くことができ、円滑なコミュニケーションができる人
- リーダーシップも取れる人
正直、こういう人は【男性保育士に向いてない人】かもしれない…
- 子どもが苦手、うるさいと感じてしまう人
- 短気ですぐに感情的になってしまう人
- 女性中心の職場に適応する努力ができない人
- 汚れたり、計画通りに進まなかったりすることに強いストレスを感じる人
あなた自身がどんな人なのか?どんな保育ができるのか?それを考えるきっかけになれば嬉しいです。
男性保育士の未来は明るい!資格を活用して自分らしい保育をしよう
男性保育士は、まだまだ少数派かもしれません。だからこそ、あなたが業界の新しい道を切り拓くパイオニアになれる可能性があります。
かつて「女性の職場」とされてきた保育業界も、今は変化の時を迎えています。今後、男性保育士の需要はさらに高まり、活躍の場も広がっていくでしょう。
そして、保育現場で得られる経験は、園の中だけで終わるものではありません。
その専門性を活かして自分で保育ビジネスを始めたり、異業種と連携して新しいサービスを生み出したりと、あなたのキャリアには様々な可能性があるのです。
保育士なら異業種転職も. 職場は保育園だけじゃない!保育士資格・免許、経験を活かせる保育園以外の求人、一般企業、稼げる仕事、働ける場所


免許資格経験活かせる幼稚園以外の仕事、働ける場所、転職先.一般企業求人ある?.jpg)