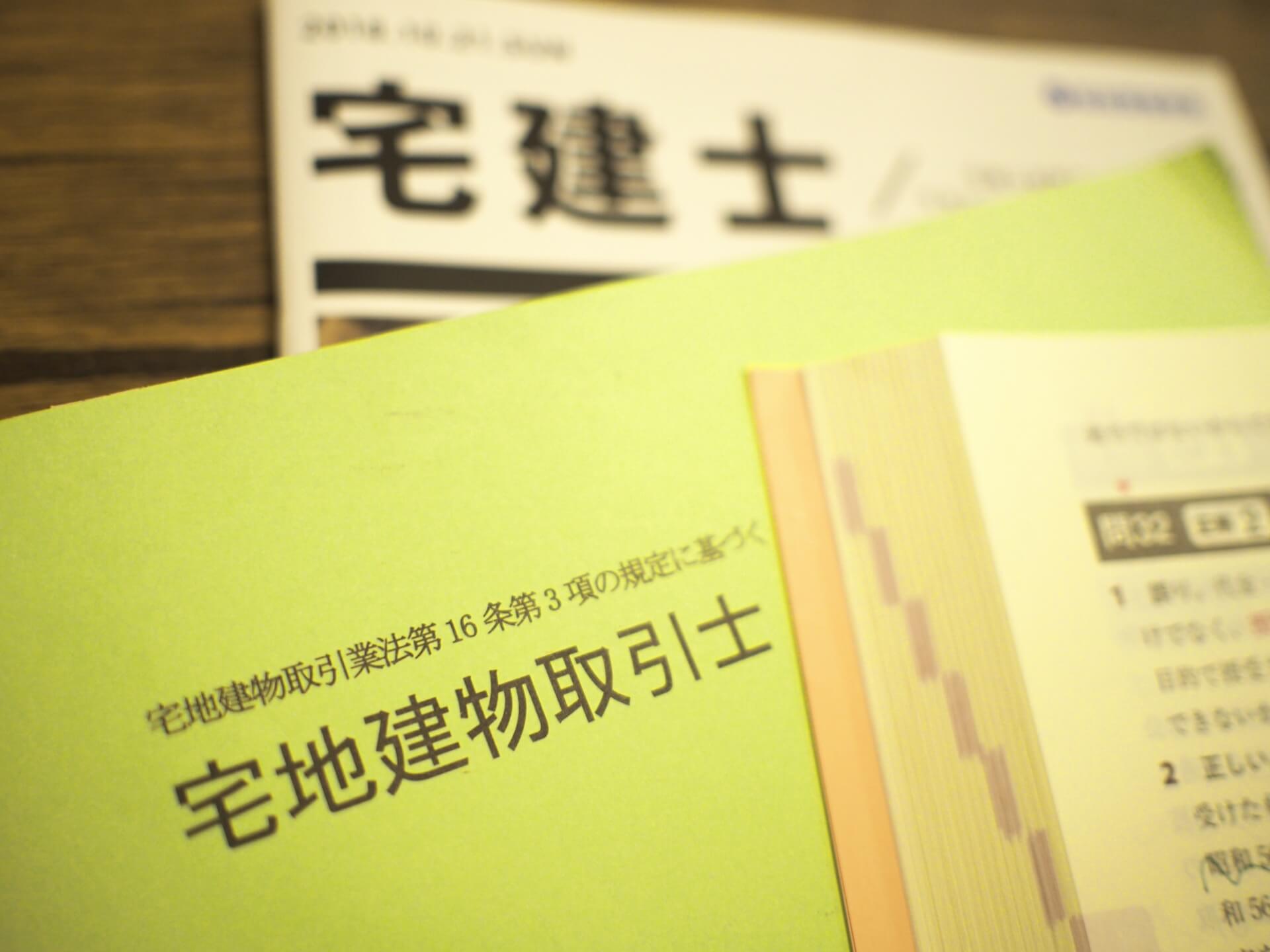[本ページはプロモーションが含まれています]
私は2023年(令和5年)の試験に独学で挑戦し、幸いにも一発合格することができました。
この年の合格ラインは36点。結果として、私はちょうど36点でギリギリの合格でした。受験生なら多くの方がそうだと思いますが、私も問題用紙に自分の解答を控えておき、自己採点に備えていました。当日の夜は、YouTube Liveの解答速報を確認しながら自己採点を実施。
ただ、その時点で大手専門学校3社が「合格予想ラインは37点」と発表しており、「もしかしたら今年はダメかもしれない…」と、不安で落ち着かない夜を過ごしたのを覚えています。
宅建士を目指した一番の動機は、将来のキャリアの幅を広げたいと考えたからです。私はこれまでにいくつか資格を取得していますが、その中でも宅建士は「独占業務がある」や「事業所ごとに配置義務がある」という点で強みを感じました。「一生モノの国家資格」として、私のキャリアを支える大きな武器になると確信して挑戦しました。
また、年齢を重ねるにつれて記憶力や瞬発力が少しずつ落ちているのを実感していました。だからこそ「30代のうちに取得しておきたい」という思いも強くありました。
宅建士の試験内容と合格の難しさ、おすすめ独学方法、学習時間、テキストなど
宅建士の試験内容
宅建士試験は年齢や学歴、職歴などの制限が一切なく、誰でも受験することができます。試験形式はすべてマークシート方式で論述問題がないため、他資格に比べて取り組みやすい点も特徴です。
試験は毎年10月第3日曜日に実施され、時間は午後1時から午後3時までの2時間です。年に一度しかないため、不合格となった場合には翌年まで待たなければならず、モチベーションの維持が課題になります。
また午後開始ということもあり、昼食後の眠気対策や体調管理も大切なポイントでした。
宅建士合格の難しさ
私はFP1級も取得していますが、宅建士試験の難易度はFP1級と同程度だと感じました。
宅建士試験の合格率はおよそ17%前後と一見低く見えます。ただし、宅建士には受験資格がなく、誰でも気軽に受験できることから、合格率が下がっている面もあると思います。
試験は大きく4つの分野で構成されています。
- 宅建業法
- 民法等(権利関係)
- 法令上の制限
- 税・その他
合格点は毎年35点前後で推移しており、年度ごとに難易度や合格点が変動します。特に宅建業法は全体の約4割を占めるため、ここを重点的に得点できるかどうかが合否を分ける大きなポイントです。
宅建士試験の難しさの一因は、学習範囲の膨大さと暗記量の多さにあります。とりわけ、法律に馴染みのない人にとっては、最初のハードルは「法律用語に慣れること」です。初めて目にする専門用語の意味を理解きるようになるまでには、それなりの時間と労力がかかります。
特に試験全体の約4割を占める宅建業法では、こうした法律用語が次々に登場します。
————————————————
【宅地建物取引士資格試験令和6年度問題【問38】】
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
2 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
3 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
4 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第 3 条の 2 に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
【解答】4
————————————————
独学の勉強時間、勉強方法、使用したテキスト、4か月のスケジュール
勉強時間
私が宅建試験に取り組んだ期間は4か月、総勉強時間はおよそ400時間でした。通信教育や専門学校は利用せず、完全に独学で挑みました。
テキスト・教材
基礎知識のインプットには市販テキストとYouTube講義をフル活用しています。
メイン教材はTAC出版の「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」(第1~3分冊)。A5サイズで軽く、持ち運びに便利なのが大きな魅力でした。さらに索引が付いているため、調べ物がしやすいのもポイントです。
 | 2026年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 [ 滝澤 ななみ ] 価格:3300円 |
![]()
個人的な意見ですが、索引がないテキストは確認作業に手間取るのでおすすめできません。
直前期には同じくTAC出版の「本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士」を利用しました。模試が5回分収録されており、私は専門学校が実施する公開模試には参加せず、この一冊で仕上げました。
 | 2025年度版 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 [ TAC宅建士講座 ] 価格:1760円 |
![]()
過去問については、一般財団法人不動産適正取引推進機構のHPで無料配布されている直近3年分をダウンロードして印刷しました。法改正の影響を考慮し、それ以前の年度は切り捨てています。さらに、通勤や休憩時間にはスマホアプリで一問一答を繰り返し、理解が浅い箇所はスクリーンショットを保存。その日のうちに条文やテキストで補強するという「即日フィードバックルール」を徹底しました。
4か月のスケジュール
試験4か月前(インプット期)
まずは全体像の把握を優先し、テキストを1周読み流し。併せてYouTubeの講義もすべて視聴し、知識の土台を固めました。2周目では条文や用語を理解できるレベルまで掘り下げています。
試験3か月前(アウトプット開始期)
模試5回分と過去問3年分を解き始めますが、この時点では点数や制限時間は気にしません。大切なのは解説を読み込み、テキストに直接書き込んで知識を集約することです。
私はノートを別に作らず、すべての情報をテキストに集約しました。付箋やコピーを貼って、自分専用の「ノート一体型テキスト」を仕上げていく方法です。
これはおすすめです。ノートを作るより効率的で、見返すときも迷いません。
試験2か月前(タイムトライアル期)
模試と過去問を120分で解く練習を開始。Excelで進捗管理表を作り、日付・得点・取り組み回数を記録しました。これにより「どれくらい演習を積んだか」が可視化され、自信につながります。早朝に演習と採点を済ませ、夜に未解答や誤答の解説を徹底的に復習。この時期の得点は30点前後でしたが、弱点補強を最優先にしました。
試験1か月前(仕上げ期)
早朝のタイムトライアルを継続し、安定して48~50点を取れるよう仕上げます。加えて、暗記が必要な分野(建築確認、開発許可、宅地造成、時効、借地権、免税点など)を毎日紙に書いて反復。最初は見ながらでないと書けませんが、繰り返すうちに反射的に書けるようになり、本番での対応力を高めました。
このように「インプット期 → アウトプット期 → タイムトライアル期 → 仕上げ期」という段階を踏むことで、独学でも効率よく合格レベルに到達できたと思います。
勉強で苦労したこと
一番苦労したのは宅建業法と権利関係(民法)でした。
宅建業法では、35条書面や37条書面の記載事項を「売買・交換」「賃貸」で比較しながら暗記する必要があります。不動産業界の経験がなかった私には、とてもハードルが高く感じました。覚えたはずの数字を次の日には忘れてしまい、焦りで何度も不安になったのを覚えています。最終的には、YouTube講師が紹介していた語呂合わせや紙に書き出す方法で、繰り返し定着させました。
また、権利関係(民法)は法律用語が難しく、一つの条文を理解するのに時間がかかりました。特に「相対効・絶対効」「弁済・相殺」「借地権・借家権」などはイメージがつかみにくく、理解に苦労しました。何度も読み返し、調べなら少しずつ慣れていった形です。
例えば、権利関係(民法)では、次のような問題が出題されます。
————————————————
【宅地建物取引士資格試験令和6年度問題【問6】】
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答】4
————————————————
勉強中は「昨日やったはずのことを今日また忘れている」という感覚が続き、精神的にもきつかったですが、粘り強く繰り返すことで徐々に力がついていきました。
宅建本試験での問題の解き方、対策
受験生の中には、模試や過去問を繰り返すうちに「解く順番」をあらかじめ決めて臨む方も多いと思います。
私はというと、問1から順番に解き進めていくスタイルです。
もちろん、最初に全50問をざっと見て取捨選択するやり方も有効ですが、私にはその時間すら惜しく感じられたので、頭から解答していく方法を選びました。
とはいえ、読んだ瞬間に「これは無理」と感じた問題については、きっぱり後回しにしていました。
解き方にも自分なりのルールを設けていました。
たとえば「自信がないから後で見直したい」と思った問題には星マークをつけ、「これは腰を据えて考えないと解けない」と判断した問題には、星マークに加えてドッグイヤーを折って目印をつけるようにしていました。
本番では時間配分に追われるので、こうした工夫が大きな助けになります。
また、意外と見落としがちなのが持ち物や環境対策です。
私は「試験中に受験票が机から落ちたら…」と考えるだけで落ち着かなくなるタイプなので、受験票の裏にセロハンテープで小さな輪を作り、机に固定していました。
マークシートの消し間違いに備えて、消しやすいノック式の消しゴムを用意。さらに、試験会場の空調が強めに効いていることを想定して、ブランケットも必須アイテムでした。
細かい準備や工夫が「1点」につながります。たった1点で泣くか笑うかが決まる試験だからこそ、こうした些細な備えまで含めて勝つための戦略だと思います。
通信教育や専門学校の通学学習についての感想(独学との比較)
私が独学で宅建士試験に一発合格しましたが、これは私自身のバックグラウンドが大きく影響していると思います。
- 税理士事務所での勤務経験があり、税法や民法にある程度の知識があったこと
- 直前にFP2級を取得しており、不動産や相続に関する知識が新しい状態だったこと
こうした下地があったため、独学でも効果的に学習を進められました。
一方で、法律の学習が初めての方や学習習慣がない方にとっては、通信講座や専門学校に通う方が効率的だと思います。体系的に学べたり、講師の解説で理解を深められる点は大きなメリットです。
ただ、通信講座や通学を利用しても、結局は「教材を繰り返し解いて定着させること」が合格のカギだと思います。私は独学を通じて、自己管理力や勉強習慣を強化できた点が大きな財産になりました。
他の受験生と比べたり、さまざまな教材に手を出して不安を抱えるよりも、最初に決めた教材を信じて繰り返すことが精神的な安定につながります。私自身も、そのやり方を貫いたからこそ、最後までブレずに勉強を続け、合格まで走り切れたのだと思います。