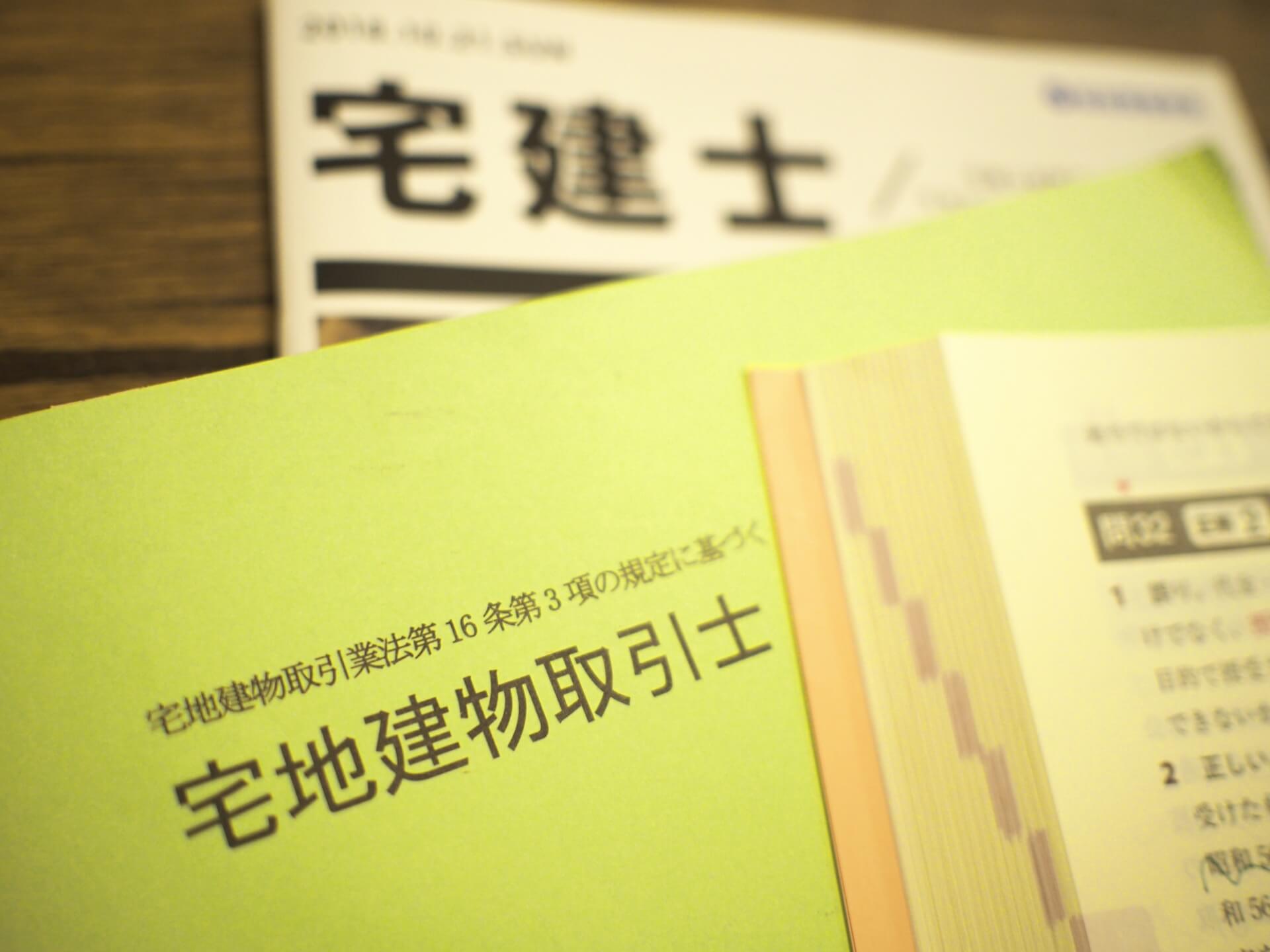[本ページはプロモーションが含まれています]
宅建士資格を目指したのは、FP資格からのつながりです。
もともと暮らしにかかわる実用的な知識を独学で身につけて日常生活に役立てたいという思いから、まずお金にかかわるFPの勉強に取り組んでいたところ、不動産の分野については宅建士資格があることを知りました。
この資格では家の売買や賃貸借など実生活にそのまま活かせる知識を習得することができます。
そこで、2022年7月にFP資格を取得した後に、宅建士試験の勉強を始めることにしました。
10月の試験までは3か月ほどの期間でしたが、少しでも効率的に勉強できるよう工夫して取り組み、初めての受験で合格することができました。
宅建士試験内容と宅建士資格取得の難易度、独学の勉強の仕方、勉強時間、テキスト、おすすめ勉強法など
宅建士試験内容の紹介
出題分野と出題数は、
①「権利関係」分野から14問、
②「宅建業法・関係法令」分野から20問、
③「法令上の制限」分野から8問、
④「税・その他」分野から8問で、
出題数の合計は50問です。
また、試験方法は4肢択一式の筆記試験(マークシート方式)で、試験時間は2時間です。
問題の形式は、全50問のうち9割程度は正誤を問う設問に対して4つの選択肢のうちから正解を1つ選ぶ「正誤」問題で、あとの1割程度は設問について正しい肢または誤りの肢の数の正解を選ぶ「個数」問題となっています。
宅建士資格取得の難易度
宅建士試験の合格率は例年15%程度ですが、直近3年(2022~2024年度)は18%程度に上昇しています。合格率としては高くはありませんが、他の国家試験(社労士や行政書士)と比べると宅建士の合格率は高めで、国家資格の中では比較的合格しやすい試験です。
また、合格基準点は例年50問中35問(7割)前後で、直近3年は36~37問となっています。合格基準点としては他の資格試験は6割程度が多い中、宅建士試験では高得点をとらなければなりません。
このように宅建士試験は決して簡単な試験ではありませんが、他の国家資格と比較すると難易度は低いといえます。
独学の勉強の仕方、勉強時間、使用したテキスト
〈独学の勉強の仕方〉
資格試験に独学で合格するには、その試験の特徴をつかんで効率的な勉強の仕方をする必要があります。
宅建士試験では直近の合格基準点の最高が38問(2020年度)となっていたことから40問を目標にして、7割の出題ウエイトを占める宅建業法・関係法令分野、権利関係分野とそれ以外の分野とで、勉強の仕方を変えて取り組みました。
この2分野については得意分野にして得点源とするため、全体像の把握と試験で問われる知識の理解を重視して「テキスト」を勉強の軸にしました。
どこに重点を置いて勉強すればよいかを明確にするために、まずはテキストを読み、全体像がざっくり把握できた段階で、すぐに過去問を解くようにしました。
過去問題集に取り組むときは、わからない問題はすぐに解答を見て解説を読み、次にテキストに戻って確認しました。
このようにして過去問題集を何度か解いてみると、試験で出題される範囲とレベルがわかり、テキストの中で押さえておくべきポイントをつかむことができました。
そして、そのポイントに重点を置きながらテキストを繰り返し読んでいくと、全体の理解も深まっていきました。
それ以外の分野については、これまでに出題された知識の習得を重視して「過去問題集」を勉強の軸にしました。
テキストは主に辞書として使用することにして、テキストを数回読んでから、すぐに過去問題集に取り組むことにしました。
そして、過去問題集に取り組むときは、問題を読むとすぐに解答を見て、解説をしっかりと読み、解説から知識を習得することにして、必要に応じてテキストで確認するようにしました。
過去問題集を繰り返すことで、勉強すべき範囲が明確になり、頻出の知識や関連知識を習得することができました。
その結果、試験は、権利関係分野13問、宅建業法・関係法令分野17問、法令上の制限分野6問、税・その他分野8問の合計44問正解(合格基準点36問)でした。
〈勉強時間〉
平日1時間と土日4時間を基本に1週間で13時間(試験直前の2週間は20時間)は勉強に充て、試験までの3か月間の勉強時間としては200時間程度でした。
〈使用したテキスト〉
テキストは、網羅性が高いものがよいと考え、直近12年間の出題実績を踏まえた内容となっている点から、『パーフェクト宅建士 基本書』(住宅新報出版)を使用しました。解説がわかりやすく整理されていて、ポイントを理解するのに役立ちました。
 | 2026年版 パーフェクト宅建士 基本書 [ 住宅新報出版 ] 価格:3080円 |
![]()
また、過去問については、1988年度以降の試験の問題と正解は不動産適正取引推進機構のHPから入手できますが、法改正は反映されていません。そこで、過去問題集として、直近12年間のすべての問題を掲載している『スッキリとける宅建士 論点別12年過去問題集』(TAC出版)を使用しました。
 | 2025年度版 スッキリとける宅建士 論点別12年過去問題集 [ 中村 喜久夫 ] 価格:2860円 |
![]()
問題数は多いですが、試験で問われる知識はほぼ網羅され、問題には重要度が示されているのでメリハリをつけて勉強するのに役立ちました。
なお、過去問で勉強するときは、一問一答方式で丁寧に解き、あやふやな知識があれば必ず解説で確認するようにしました。
勉強でしんどかったこと
FPの勉強をしていたので宅建士試験ではとっつきにくい科目はありませんでしたが、どの科目も覚えなければいけない数値が多く、試験の直前に詰め込んで暗記しました。
宅建士試験に受かるには?受かるコツ
宅建士試験に合格するには、テキストや問題集に示されている基本知識を確実に定着させることがなによりも大切です。特に過去に出題された基本知識は試験問題を解くときの最大の武器になり、問題の6割程度は正答することができます。
過去に出題された内容について理解して記憶していくには、過去問題集とテキストの往復を何回も繰り返すことが有効です。
住宅瑕疵担保履行法や農地法は過去問を繰り返すだけで得点できます。
ただし、宅建士試験は範囲が広いので、勉強する内容を絞り込むことが必要になります。それには早めに過去問題集を解いて、出題の傾向と問題のレベルを把握するのが効率的です。こうした「絞り込み」と「繰り返し」によって、知識を定着させていくことができます。
さらに、知識をインプットしたとしても、その知識を試験の制限時間内に的確にアウトプットできなければ、試験に合格することはできません。試験では問題を「正確に、かつ、速く解く」ことが必要になります。
それには、まず、問題ごとに選択肢を解く前に「判断しやすい選択肢を探す」ことです。
試験では、個数問題を除いて、すべての選択肢の正誤を判断する必要はなく、答えを1つ探せばいいので、検討する選択肢の数を少なくすれば短時間で問題を解くことができます。
そこで、選択肢の上から順に解いていくのではなく、まず選択肢を全肢ざっとナナメ読みをして、過去問に類似した選択肢、文中に得意なキーワードがある選択肢、文書が短い選択肢を探して、判断しやすい選択肢から解くことをおすすめします。
また、計算が必要な選択肢は時間がかかるので後回しにして、他の選択肢で答えが出ないときに最後に解くようにします。計算が不要な選択肢で答えが出せたら、計算が必要な選択肢は解かなくて済みます。
そして、選択肢を解くときは「確実な知識だけで判断する」ことです。あやふやな知識は判断を迷わせるので、自信がある知識に基づいて選択肢の正誤を判断し、わからない選択肢はあえて判断しないようにします。
わからない選択肢があったとしても、判断できた選択肢だけで設問の答えを出せることが多くあります。
このようにして、試験では、「絞り込み」と「繰り返し」により効率的にインプットした知識を、「正確に、かつ、速く解く」方法を使って効果的にアウトプットすることで、着実に合格基準点に到達できます。