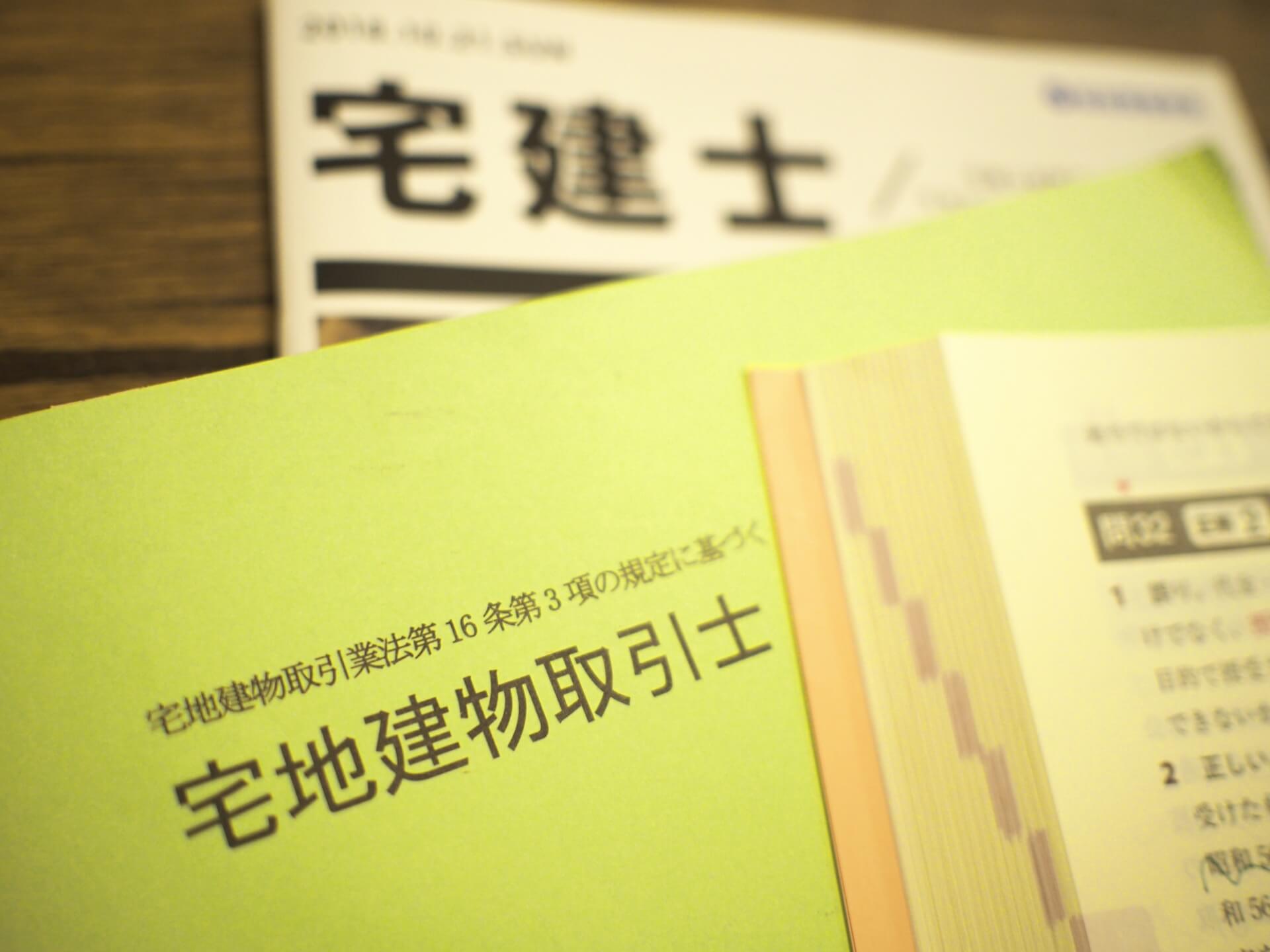[本ページはプロモーションが含まれています]
私が宅建士を取得したのは、社会人1年目の時です。
文学科の大学ということもあり、知識0からハウスメーカーに入社したため仕事に直結する勉強がしたいと思い宅建士の資格取得を目指しました。
また、重要事項説明などができるようになり、自身の業務の幅が広がると先輩に教えてもらったこともきっかけの一つです。
そんな私が、どうやって働きながら宅建士試験を合格したのか、またその後、仕事にどのように活かすことができたかなど実体験を踏まえてお話していきます。
宅地建物取引士試験内容と独学の勉強方法
まずは、宅地建物取引士試験の試験概要と、社会人1年目で働きながら宅建士資格を取得することができた私なりのおすすめ勉強法をご紹介していきます。
宅地建物取引士試験内容の紹介
- 試験日:毎年10月 第3日曜日(年1回)
- 試験時間:2時間 13:00~15:00
- 問題形式:4択マークシート 全50問
- 受験条件:特になし
「権利関係(民法)」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」の大きく4つの分野に分かれています。
宅建士資格取得の難易度

国家資格でもある宅地建物取引士は、合格率としては毎年15~17%と決して高くはなく、他の国家試験と比較すると中間くらいの難易度となっています。
一定の合格率を保つ目的で、毎年のように合格ラインが変動しており、おおよそ35~37点が合格ラインとなっています。
年々、受験者数が増えていることもあり、合格ラインは上昇傾向にあることも抑えておくとよいでしょう。
独学の勉強の仕方、勉強時間、使用したテキスト

わたしは独学で勉強をしていました。
主に使用したのは以下の3つの媒体です。
- テキスト:『出る順宅建士合格テキスト』(東京リーガルマインド)
2026年版 出る順宅建士 合格テキスト 1 権利関係
2026年版 出る順宅建士 合格テキスト 2 宅建業法
2026年版 出る順宅建士 合格テキスト 3 法令上の制限・税・その他 - 過去問集『わかって合格(うか)る宅建士 過去問12年PLUS』(TAC出版)
- YouTube
まず、テキストは本屋で購入したLECさんのものを使用していました。
個人的にカラフルすぎるテキストよりも、2~3色でまとまっている方が、重要な箇所が分かりやすいと感じていたため、シンプルかどうかを基準に選んでいます。
次に、過去問集もテキスト同様に本屋で購入したものです。
テキストはシンプルさを重視しましたが、過去問集に関しては、問題数の多さを重視して12年分の過去問が掲載されているものを選びました。
ちなみに問題集や模擬試験ができるテキストもありましたが、そちらは購入していません。
最後に、YouTubeに関しては、何人か宅地建物取引士試験の解説動画を出している方いるので、自分のフィーリングに合った人を選んで視聴しました。
時間を作ってじっくり見る、というよりは移動時間に音声だけ聞いたり、家事をしながら流したりと「ながら作業用」として活用していました。
宅建士試験は問題の文章量が多いだけでなく、難しい言葉や聞きなれない単語が多く登場します。
初めて受験する方は特に、宅建士試験の専門用語に慣れるためにも、動画を活用して日常的に勉強することがおすすめです。
これらの媒体をつかって、5月から本格的に勉強を開始。そこから10月まで約400時間をかけて勉強しました。
実は、受験自体は2回目での合格になります。
大学4年生のとき、7月頃から勉強を始めて”記念受験”感覚で1回目を受験していました。
約3か月で60時間ほどしか勉強をしておらず、点数も27点と悲惨な結果でした。
ですが、この3か月間があったおかげで、2回目の受験ではどのくらい勉強時間を確保するべきか、どのように勉強をするべきかなど作戦を立てることができたと思っています。
これを読んでくださる皆さんには、ぜひ1度の受験で合格していただきたいので、下記でさらにおすすめの勉強法なども紹介していきますね。
宅建士の勉強でしんどかったこと

勉強をしていると、もちろん大変なことも出てきます。
特に、仕事と両立して勉強をしていたので時間の確保だったり、仕事終わりで眠気との戦いになったりとスケジュールと体調管理が大変でした。
社会人になると、時間との戦いです。
私は、仕事がある日でも必ず1時間は勉強すると決めていましたが、残業や眠気は最大の敵でした。
そこで、帰宅後の勉強は早々に諦め、朝に早起きして1時間は勉強するという方法に切り替えるなど工夫をしたつもりです。
無理に勉強をしすぎて、仕事で集中できなくなったり体調を壊してしまったりしては、本末転倒です。
一度、計画を立てたとしても日々の生活に合わせて、柔軟に練り直していくことも必要だと思います。
宅建に受かるには?受かるコツは?

- ①テキストのインプットより過去問のアウトプット
- ②出題傾向に合わせて勉強する範囲を絞る
私が意識していたのは、このたった2つのことです。
まず①について、テキストと過去問の割合は2:8くらいで活用するよう心掛けました。
テキストでインプットしようとしても難しい言葉や、聴きなじみのない単語ばかりで覚えきれません。
最初にテキストを2周ほどさらりと読んで全体像を把握できたら、そこからは過去問を解いて間違えたところ、分かりにくいところをテキストで調べるとよいでしょう。
あとはその繰り返しです。
次に②ですが、①のように過去問を進めることで、試験の出題範囲や傾向を掴めるようになります。掴めてきたら、徐々に勉強するテーマを絞っていくことで効率よく勉強ができます。
例えば、問題数が多く出題される「宅建業法」の分野を重点的に勉強する、「権利関係」は頻出テーマのみ覚えて他の問題は棄てる、などです。
各分野の大まかな問題数は以下の通りとなっています。(括弧内は私が合格した時の点数です)
- 権利関係(民法):14問(7問)
- 宅建業法:20問(19問)
- 法令上の制限:8問(8問)
- 税・その他:8問(6問)
これをみると、「宅建業法」と「法令上の制限」だけで全問題数の5割以上を占めていることが分かります。
この2つの分野で満点近くの点数がとれれば、合格まで残り6~10問ほど正解するだけで合格圏内に入れる計算となるのです。
実際に私は、「宅建業法」と「法令上の制限」は満点に近い点数を取ることができました。一方で「権利関係」は頻出テーマのみを勉強し、それ以外は棄てて試験に臨んだため半分の点数しか取れていません。
それでも40点を取ることができ無事に合格でした。
特に「権利関係」は、過去問を対策していたとしても、試験で初めて見る問題や事例が出題されることがしばしばあります。
そのため、早々に割り切ってあまり時間をかけすぎないことがポイントです。
このように問題の傾向を掴んだうえで勉強を進めると合格に近づけることでしょう。
もちろん、この方法は賛否両論だと思います。
人によって宅建士を目指す目的は様々だと思いますが、私はまず「合格」することが目標だったので、いかに限られた時間で効率よく勉強するかを重視していました。
ハウスメーカーでの宅建士の仕事のしんどいこと

宅建士を持ってハウスメーカーで働いていると大変な一面もあります。
宅建士の数が少ないハウスメーカーでは、他の営業のサポートをしたり、仕事を代わりに任されたりすることが数多くあります。
例えば、自社の土地や建売を販売する時に行う重要事項説明などで、宅建士を持っていない他の営業マンから仕事を頼まれることがあります。
そのため、自分の顧客以外にかける時間が増えてしまったり、打ち合わせのスケジュール調整をしたりする必要が出てくるのです。
また、書面の用意は他の部署で行ってくれることが多いですが、他の営業マンの顧客とはいえ正しい内容を分かりやすく伝えなければいけません。
その準備として、内容に誤りがないかの確認や情報・知識の補完、担当の営業マンと当日の流れのすり合わせなどが必要になります。
このように、自分の顧客以外で日程調整や事前準備に時間を割かなければいけないところは、ハウスメーカーの宅建士の大変なところです。
さらに、宅建士として他の営業マンや他部署からも質問を受けることがあり、勉強になりつつも自分のスケジュールが詰まっているとやることが増えて、しんどいと感じることがありました。
ハウスメーカーでの宅建士の誇り、やりがい

ハウスメーカーの営業の場合、不動産屋の営業と比較し有資格者の割合が少ない傾向にあります。
ハウスメーカーが不動産取引よりも建築請負業務がメインとなるためです。
だからこそ、営業マンが宅建士であるかどうかで、お客様からの第一印象や信頼度が変わります。
営業マン同士で比較された時に、より好印象を与えられ、差別化を謀ることができるのです。
例えば宅建士だからという理由で、顧客が所有している土地の複雑な権利関係について相談を受け、真摯に対応したら間取りや資金の提案をする前に契約をしてもったことがあります。
このような「宅建士」という資格をきっかけに、他の営業マンには相談していないような問題や悩みを打ち明けてくれることがあり、それに応えることで顧客との信頼関係を築けるようになるのです。
営業マンとしても宅建士としても顧客から頼られているときは、とてもやりがいを感じられます。
宅建士のハウスメーカーでの収入・待遇
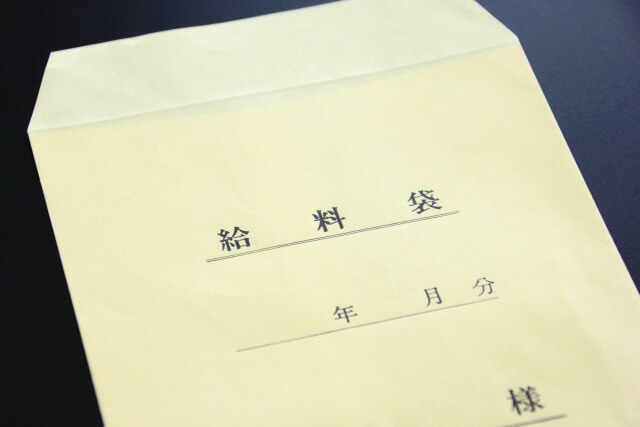
宅建士になることで、会社によっては優遇を受けることができます。
私の会社では、資格取得時に御祝い金がもらえたり、その後も毎月の給料に資格手当がついたりといった優遇措置があります。
先述した通り、ハウスメーカーの営業は不動産屋と違い、業務するうえで必ずしも宅建士の資格が必要というわけではありません。
だからこそ、宅建士であることは社内での評価UPにつながり、会社ごとに給料面で優遇を受けられる場合が多いのです。
宅建士を目指す方へ

宅地建物取引士試験は簡単に取得できる資格ではありません。
実際に、私の上司や上司の中には毎年受験しても合格できない人が数多くいます。
自分で決めたことをやりきるという意思が強い人は独学でも大丈夫ですが、モチベーションが続かない人や勉強時間が確保できるか心配な人は、通信講座や塾に通うべきでしょう。
しかし、取得できれば顧客から専門的な相談を受けるようになったり、難しい提案もできるようになったりと仕事に直結する資格です。
実際に業務をするうえで学んだ知識も活かせましたし何よりも、努力して合格できたという実績は自分の自信に繋がります。
宅建士を本気で目指したいみなさん、社会人でも時間を設けつつポイントを押さえた勉強ができれば合格できる試験だと思いますので頑張ってみてください。